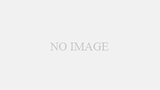こんにちは、Madonna Village編集部です。
毎日忙しく働いていると、国会でどんな話がされているかなんて、なかなか気にする余裕ないですよね。でも、私たちの生活に直結する大切な話がたくさんされています。
2025年1月24日、柳ヶ瀬裕文議員から提出された「税収弾性値の算出に用いる計算式等に関する質問主意書」を元に、今回は税収弾性値について考えてみたいと思います。
■税収弾性値(ぜいしゅうだんせいち)とは
「経済がどれくらい成長すれば、税収がどれくらい増えるか」を示す指標です。たとえば弾性値が1.1なら、経済が1%成長したときに税収は1.1%増える、という意味になります。
この数値は、政府が将来の税収を見積もる際に使われ、予算の見通しや財政計画に大きな影響を与えます。しかし、どの期間のデータを使うか、どんな経済状況を前提にするかで数値は変わってしまうため、使い方や妥当性には慎重な議論が必要です。数字の裏にある前提条件や考え方を見極めることが、政策の理解には欠かせません。
この議論、そもそも何が話されているの?
税収弾性値とは、名目経済成長率に対する税収の伸び率のことであり、政府の中期的な税収見通しを立てる際に用いられる重要な指標です。
質問主意書では、柳ヶ瀬議員がこの税収弾性値の算出方法やその背景について、政府に対して詳細な説明を求めています。
特に、過去のデータをどのように使用しているか、そしてその結果が現実の経済状況をどれだけ正確に反映しているのかに焦点が当てられています。
質問と答弁、全て見てみよう
❓ 質問1:税収弾性値の具体的な算出過程について
柳ヶ瀬議員は、令和六年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算において、実際に用いた各年度の税収と名目GDPの値を示すよう求めています。
💬 政府の答え:細かいデータを提示
政府は、昭和五十一年度から令和元年度までの各年度における税収の伸び率と名目経済成長率の具体的な数値を詳細に示しました。
📝 編集部EYES:具体的なデータで透明性を確保
政府は具体的なデータを提示することで、税収弾性値の算出過程の透明性を確保しようとしていますが、このデータが実際の経済状況をどれだけ正確に反映しているかは議論の余地があります。
❓ 質問2:税収弾性値の使用目的について
税収弾性値を用いる目的は何か、またそれに誤りがないかを確認しています。
💬 政府の答え:中期的な税収見通しのため
政府は、税収弾性値を用いる目的として、中期的な税収見通しを機械的に試算するためであると回答しました。
📝 編集部EYES:目的は明確だが、運用の妥当性は?
目的自体は明確ですが、その運用が現実の経済状況とどれだけ一致しているかについては、さらなる検証が必要かもしれません。
❓ 質問3:中期的な税収見通しの「中期」とは
中期的とは具体的に何年間を指すのかを尋ねています。
💬 政府の答え:3年間を中期と定義
政府は、令和八年度から令和十年度までの3年間を中期と定義しています。
📝 編集部EYES:3年間が中期とされる理由は?
なぜ3年間が中期とされるのか、その理由や背景についての説明が不足しているように感じます。
❓ 質問4:税収弾性値1.1の算出に用いた期間について
過去の具体的な期間が適切かどうかを確認しています。
💬 政府の答え:昭和45年度から54年度の平均を使用
政府は、昭和45年度から54年度までの平均税収弾性値を基にしていると回答しました。
📝 編集部EYES:過去のデータの有効性は?
過去のデータを使用することの有効性や、それが現代においても妥当であるかの検証が必要です。
❓ 質問5:過去10年間の平均を用いる理由について
なぜ過去10年間の平均を用いるのか、その理由を問いただしています。
💬 政府の答え:安定したデータを求めて
政府は、安定した経済成長を実現していた過去のデータを用いることで、安定性を確保していると説明しています。
📝 編集部EYES:安定性と実状のバランスは?
安定性を求めることは理解できますが、実際の経済状況とのバランスをどう取っているのかが不明です。
❓ 質問6:令和六年度税収弾性値の算出日付について
具体的な算出日付とその方法を確認しています。
💬 政府の答え:特定の日付での作業ではない
政府は、特定の日付に限って作業を行ったわけではないと回答しました。
📝 編集部EYES:プロセスの詳細が不明確
作業プロセスの詳細が不明確であり、透明性の確保が求められます。
❓ 質問7:過去10年間の平均値を用いなかった理由について
過去10年間の平均値を用いず、過去44年間の平均を用いた理由を問うています。
💬 政府の答え:中長期的な視点からの判断
政府は、名目成長率の低さを考慮した中長期的な視点から判断していると説明しています。
📝 編集部EYES:中長期的視点の妥当性は?
中長期的視点が妥当であるか、再評価が必要かもしれません。
今回のやり取りから見えること
この質疑応答を通じて、税収弾性値の算出方法とその背景には、様々な経済指標が複雑に絡み合っていることが見えてきます。
政府は安定性と中長期的な視点を重視していますが、それが現実の経済状況をどれだけ反映しているのかについては、さらなる議論が必要とも見えました。
また、国の運営において「税収弾性値」というのは、本当に重要な数値であるのか?その質問をした背景や目的、意図は日本国の国益にとって重要な視点と言えるのか?もまた考えてみる必要がありそうですね。
最後に、あなた自身の問いを見つけるために
私たちは、答えを提示することはできません。
しかし、今日の話を通じて、税収弾性値がどのようにあなたの生活に影響を与えるのか、そしてその算出方法が本当に妥当なのか、あなた自身で考えてみてください。
次に政府がどのようにこれらのデータを使って政策を決定していくのか、一緒に見守っていきませんか?
一次情報である原文へのリンクは以下の通りです