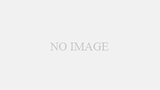こんにちは、Madonnna Village編集部です。
毎日忙しく働いていると、国会でどんな話がされているかなんて、なかなか気にする余裕ないですよね。特に、技術的な話題は難しく感じるかもしれません。しかし、政府の動きは私たちの生活に直接影響を与えることが少なくありません。
2025年1月24日、神谷宗幣議員から提出された「ガバメントクラウドとデータ主権及び経済安全保障に関する質問主意書」を元に、今回はその背景と要点について考えてみたいと思います。
ガバメントクラウドとデータ主権、なぜ今議論されているのか?
ガバメントクラウドの導入が進む中、海外のクラウドサービスに依存することへの懸念が指摘されています。
そのため、データ主権や経済安全保障の観点から、国内のクラウドサービス提供事業者を育成する必要性が議論されている用にも見えました。
このような背景があるため神谷議員は、地方自治体に対して日本企業のクラウドサービスを選択肢として提供するための施策について質問しているようにも見えます。なぜなら地方自治体が外国企業のクラウドサービスに依存せざるを得ない現状があるという見方をしているからです。
■ガバメントクラウドの基本情報と日本の現状
ガバメントクラウドとは、国が整備する共通のクラウド基盤で、全国の自治体が行政システムを一元的に利用できる仕組みです。業務の標準化やコスト削減、災害時の安全性向上などが期待されています。ただし、現時点では海外IT企業のクラウドが主流で、個人情報などが海外のサーバーに保存される「データ主権」の問題や、乗り換え困難な「ロックイン」リスクも指摘されています。政府は日本企業の参入促進や技術支援を進めていますが、地方自治体にとっては選択肢が限られており、移行には課題も残されています。
質問と答弁、全て見てみよう
❓ 質問1:日本企業のクラウドサービス育成施策について
神谷議員は、地方自治体が外国企業のクラウドサービス以外の選択肢を持つために、日本企業のクラウドサービス提供事業者への支援や補助金の具体策を尋ねました。
💬 政府の答え:新規事業者の参入を促進し、技術開発を補助
政府は、デジタル庁が日本企業の参入を促進するための仕様書を設け、さくらインターネット株式会社と契約を締結したこと、さらに経済産業省が技術開発に対する補助を行っていることを説明しました。
📝 編集部EYES:具体的な施策は進んでいるが、現状での選択肢は限られる
日本企業の参入を促進する施策はあるものの、現時点で地方自治体が選択できる日本企業のクラウドサービスは限られているようです。
❓ 質問2:オンプレミス継続に対する補助金不支給の理由
地方自治体がオンプレミスを継続する場合に補助金が支給されない理由と、オンプレミス継続を支援する施策の予定について尋ねました。
💬 政府の答え:クラウド技術活用が行政運営の合理化に寄与
政府は、クラウド技術の活用が行政の合理化に寄与すると考え、補助金はクラウドサービスに関連する技術を活用する場合に交付されると回答しました。オンプレミス継続を支援する施策は予定していないとしています。
📝 編集部EYES:オンプレミス継続の選択肢は狭まる一方か
現状では、オンプレミスを選択する地方自治体にとっては、補助金を受けられないことで選択肢が狭まる可能性があります。
■オンプレミスの意味と日本の現状
オンプレミス(On-Premises)とは、サーバーやシステムを自前で保有・運用する方法のことです。役所の庁舎内などにサーバーを設置し、自治体自身が管理します。セキュリティや運用方法を自らコントロールできる一方で、設備費や保守の手間が大きいという特徴があります。
現在、政府はクラウド活用を推進しており、オンプレミスを続ける場合には補助金を出さない方針を取っています。そのため、一部の自治体では「従来通りの運用を望んでも、予算的に難しい」という声もあり、実質的にクラウド一択になりつつある状況です。
❓ 質問3:クラウドロックイン回避のための見直し機会
一度選択したクラウドサービスを見直す機会を設けるための費用助成について尋ねました。
💬 政府の答え:データ移行を容易にする要件を設けている
政府は、データのインポート・エクスポートを容易にするツールやサポートサービスを提供する要件を設けており、地方自治体が容易に見直しを行えるようにしていると回答しました。
📝 編集部EYES:見直しの仕組みは整備されつつあるが、実効性は?
見直しを容易にする仕組みはあるものの、実際にどれだけ利用されるかは注視する必要がありそうです。
❓ 質問4:移行スケジュールの問題と対策について
地方自治体の一斉移行による問題と、その対策について尋ねました。
💬 政府の答え:移行時期の分散と支援を継続
政府は、早期移行計画の策定や事業者の決定を支援し、移行時期を分散させる方針であると回答しました。
📝 編集部EYES:計画の分散は可能か?現場の負担が懸念される
計画の分散がどの程度実行可能か、現場の負担が懸念されます。
❓ 質問5:ガバメントクラウドの利用料見通し
ガバメントクラウドの利用料の見通しとその算出方法について尋ねました。
💬 政府の答え:現時点での契約が未締結であり、見通しは困難
現時点で契約が締結されておらず、正確な見通しを立てるのは困難であると回答しました。
📝 編集部EYES:費用の不透明さが予算管理に影響を与える可能性
費用の見通しが不透明なことは、今後の予算管理に影響を及ぼす可能性があります。
議論を通して見えてくる構造的な課題とは
今回の質疑応答を通じて、ガバメントクラウドへの移行における日本企業の選択肢の少なさや、オンプレミス継続の支援がないことが浮き彫りになったことが大きな収穫なのではないでしょうか。
政府は新規事業者の参入を促進し、技術開発を支援しているものの、地方自治体が実際に選べる選択肢は限られています。
また、クラウド技術の活用が推奨されている一方で、オンプレミス継続を選択する自治体にとっては不利な状況が続く可能性があります。
最後に、あなた自身の問いを見つけるために
私たちは、答えを提示することはできません。
しかし、今日の議論を通じて、あなた自身が考える材料を提供できたのではないでしょうか。ガバメントクラウドの導入が進む中で、データ主権や経済安全保障について、あなたはどのように考えますか?
地方自治体の選択肢を広げるためには、どのような施策が必要だと思いますか?ぜひ、今回の話をきっかけに、あなた自身の考えを深めてみてください。