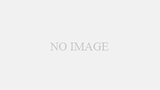MadonnaVillage編集部です。
この度は、ブログに足を運んでくださり、ありがとうございます。
突然ですが、想像してみてください。
もし、ちょんまげを落としたばかりの、
羽織袴に身を包んだ130年以上も前の国会議員たちが
タイムスリップして現代の国会に現れたとしたら──。
彼らは、今の日本の姿を見て、何と言うでしょうか。
整然と(時に野次が飛ぶ)議事進行を見て、何を思うでしょうか。そして、私たちが今、直面している課題を知った時、どんな議論を始めるでしょうか。この記事は、そんな壮大な思考実験から始まりました。
これは、歴史の全てを「物語」として再構築する
終わりなき戦いの記録です。
これからここで紐解いていくのは、明治23年(1890年)に産声を上げた「帝国議会」の膨大で、混沌とし、そして熱気に満ちた議事録のすべてです。
これは単発の記事ではありません。
古めかしい言葉で綴られたこの記録を、その始まりから終わりまで、一切の内容を省略することなく、現代の言葉で一つの連続した物語として再構築していく。そんな、気の遠くなるような旅の、まさに第一歩です。
見えなかった「国造りの現場」
私たちは、戦後の奇跡的な高度経済成長という「結果」を知っています。しかし、その礎を築いた先人たちが、どれほど複雑で、泥臭く、そして人間味あふれる議論を重ねてきたか、その「過程」を知る機会はほとんどありませんでした。
効率やスピード
分かりやすい結論ばかりが求められる現代。
私たちはいつしか、物事の本質をじっくりと考える時間を見失ってはいないでしょうか。「即断即決」がもてはやされる一方で、異なる意見に耳を傾け、たとえ時間がかかっても、全員で粘り強く一つの答えを導き出そうとする営みの尊さが、忘れ去られようとしています。
この議事録に記録されているのは、まさにその「非効率」で「混沌」とした、しかし、だからこそ真摯な議論の姿そのものです。
ルールも前例も何もない手探りの状態から、投票の方法一つで丸一日を費やし、憲法の解釈を巡って夜を徹して激論を交わす。そこには、現代の国会答弁からは見えにくい、剥き出しの情熱と、国家の未来を背負う者たちの真剣な葛藤が、ありのままに刻まれています。
これからの日本を考えるための「生きた材料」として
今、これまで「専門家の領域」とされ、私たち庶民の目からは見えにくかった国造りの現場、その裏側のやり取りが、次第に可視化される時代になりました。特に、国の方向性を左右する勢力が強まる中で、「お任せ」の政治ではなく、私たち自身がこの国の未来をどうすべきかを考え、行動することが求められています。
しかし、自分の頭で考えるためには
判断の基準となる「材料」が必要です。
このブログは、私自身がまず学ぶことを第一の目的としています。そして、この議事録という「一次情報」を、現代の言葉で一つの物語として再構築することで、かつての日本人が何を考え、何に悩み、どのようにしてこの国の形を作り上げていったのかを、皆さんと共有したいと考えています。
この記録が、これからの日本、そして私たちの議会がどうあるべきかを、私たち一人ひとりが自分の頭で考えるための、一つの「生きた材料」となることを願ってやみません。
それでは、令和の時代の私たちを、130年前の熱気と混沌に満ちた議場へと誘う、最初の証言者たちの声に、耳を傾けてみることにしましょう。
【Episode1】帝国議会の始動は嵐の船出だった
明治23年(1890年)、日本。
大日本帝国憲法が発布され、国家は新たな時代への扉を開いた。欧米列強に比肩する近代国家を目指す熱気と、まだ見ぬ「議会」という仕組みへの期待と不安が国中を包んでいた。武士の時代が終わりを告げ、国民が初めて自分たちの代表者を選んだ、その歴史的な第一回帝国議会が、今まさに幕を開けようとしていた。
議場は、まだインクの匂いが新しい西洋建築の粋を集めた建物だった。
しかし、その内部に集ったのは、羽織袴に身を包んだ男たち。彼らの多くは、幕末の動乱を生き抜き、新しい日本の形を模索してきた者たちだ。薩長土肥の出身者、自由民権運動の闘士、地方の名望家。その顔ぶれは様々で、彼らが発する言葉もまた、江戸訛り、薩摩弁、土佐弁が入り乱れていた。
ガス灯の淡い光が、
緊張と興奮に満ちた議員たちの顔を照らし出す。
これから始まるのは、単なる会議ではない。法律とは何か、予算とは何か、そして国民の代表たる議員の権利とは何か。そのすべてを、ルールすらないゼロの状態から、自分たちの手で作り上げていくという、前代未聞の壮大な実験の始まりであった。この船出が、どれほどの嵐に見舞われることになるのか、この時の彼らはまだ知る由もなかった。
【登場人物紹介:舞台に立つ者たち】
- 曾禰 荒助(そね あらすけ)
- 役職/背景: 衆議院書記官長。
- キャラクター分析: 法律に基づき議事を進行させようとするが、ルールそのものが存在しないため、議員たちの激しい議論の奔流に翻弄される。冷静沈着であろうと努めるが、議場の混乱ぶりに「私ノ眼ト根性デ認メマシタ」と本音を漏らす人間味も。
- この物語での役割: ルールなき議会の進行役という、最も困難な役回りを担う苦労人。彼の奮闘が、議会運営の礎を築いていく。
- 末松 謙澄(すえまつ けんちょう)
- 役職/背景: 福岡県選出。ケンブリッジ大学で学んだ国際派のインテリ。
- キャラクター分析: 論理的思考で、議事進行の曖昧さや非効率性を鋭く指摘する。欧米の議会を知る者として、手続きの重要性を説くが、熱気渦巻く議場では時に疎まれることも。
- この物語での役割: 議会に「近代的なルール」を導入しようとする理論家。感情論が支配しがちな議場に、冷静な視点をもたらす。
- 井上 角五郎(いのうえ かくごろう)
- 役職/背景: 広島県選出。ジャーナリスト出身。
- キャラクター分析: 情熱的で行動派。「議員の権利」が侵害されることに対して、誰よりも早く声を上げる熱血漢。
- この物語での役割: 物語の核心となる「議員不逮捕特権」問題の口火を切る重要人物。議会の権威を守ろうと奮闘する。
- 末松 三郎(すえまつ さぶろう)
- 役職/背景: 福岡県選出。
- キャラクター分析: 井上と共に、逮捕された森時之助議員の問題を徹底的に追及する。論理的かつ粘り強く、議会の特権を主張する。
- この物語での役割: 井上と共に「憲法第53条」を巡る論戦の中心となり、物語をクライマックスへと導く。
- 岡山 兼吉(おかやま けんきち)
- 役職/背景: 岡山県選出。法律家(代言人)。
- キャラクター分析: 議員の権利の重要性は理解しつつも、法律の条文解釈や議会の手続きを重んじる現実主義者。「默諾(暗黙の承諾)」という概念を持ち出し、議会の対応の遅れを指摘する。
- この物語での役割: 理想論に傾きがちな議論に、法的な視点と手続き論で一石を投じる慎重派の論客。
- 大岡 育造(おおおか いくぞう)
- 役職/背景: 山口県選出。
- キャラクター分析: 憲法の条文を厳格に解釈すべきだと主張し、末松らの意見に真っ向から反対する。外国の例を安易に持ち出すことを批判し、日本の法律の独立性を重んじる。
- この物語での役割: 「議員の権利」を主張する勢力に対する、最も強力な反対論者の一人として論戦を白熱させる。
- 中島 信行(なかじま のぶゆき)
- 役職/背景: 神奈川県選出。元土佐藩士、自由民権運動の闘士。
- キャラクター分析: 多くの議員の支持を得て、初代衆議院議長に就任。温厚だが、議場の混乱を収拾するためには毅然とした態度も示す。
- この物語での役割: 嵐の中を進む船の船長として、困難な議会運営の舵取りを担う。
第一章:ルールなき議会の誕生(明治23年11月25日)
第一幕:議会のルールは誰が決めるのか?
明治23年11月25日、午前10時。歴史的な第一回帝国議会衆議院は、議長・副議長選挙からその幕を開けた。しかし、議員たちが直面したのは、あまりにも初歩的で、しかし根本的な問題だった。
「一体、どうやって選挙をするのか?」
議事進行役を務めるのは、暫定議長として議席に立つ書記官長の曾禰荒助。彼の前には、何一つ決まっていないという現実が広がっていた。
「諸君に申し上げます」
曾禰は、緊張した面持ちで口火を切った。
「議院法第三条第二項により、私が議長の職務を行います。つきましては、本日の議長・副議長選挙について、あらかじめ皆様のご同意を得ておきたいことがございます。まず、本日の状況と結果は、速やかに記者に筆記させ、報道機関に公開したいと思いますが、ご異議はございませんか?」
議場から異議を唱える者はいなかった。
報道の自由が、議会の最初の決定事項の一つとなった瞬間だった。曾禰は続ける。
「次に、先日お配りした選挙手続きの件ですが、こちらもご異議がなければ、手続き通りに選挙を行いたいと存じます」
この言葉に、すかさず異議を唱える者が現れた。
二百五十九番、末廣重恭だった。
「動議を提出いたします! この手続きの心得書は、いかにも丁寧な手続きに見えますが、いちいちこの通り、演壇に三人ずつ登って名前を書いていては、大変な時間がかかってしまう。願わくはこれを修正し、手続きを簡略にしたい!」
末廣は、具体的な修正案を提示した。
要するに、各議員が自席で投票用紙に記入し、呼び出しに応じて順番に演壇に登り、投票箱に投函するという、より効率的な方法への変更だった。すぐさま二百七十二番、末松謙澄が賛成の声を上げる。
「ただ今の動議は、この場の混乱を防ぐのに大変よろしいかと存じますので、賛成いたします!」
曾禰は、議論が長引くことを避けようと、即座に採決の意向を示した。
「諸君に一言申し上げておきます。本日は討論は行わず、可否を直ちに起立にて問います。これも手続きを簡略化するためです。今お二方から出た動議の趣旨は、皆様すでにご理解のことと存じますので…」
しかし、ここで「待った」がかかる。六番の高梨哲四郎が、よく聞こえなかったと訴えたのだ。
「今おっしゃった動議は、我々には十分聞き取れませんでした。議長から要領をお示しになるか、あるいは動議を出された議員から、もう一度簡単にご説明いただきたい」
曾禰はわずかに眉をひそめつつも、丁寧に説明する。
「動議の要領を申しますと、『各議員が自席で投票用紙を書き、呼び出しに応じて演壇にある投票箱の中へ投票する』ということに尽きます。これにご同意の方は、ご起立ください」
パラパラと、しかし明らかに多数の議員が立ち上がった。
「多数でありますので、そのように決します」
こうして、この議会で最初のルールが、その場で決められた。だが、本当の混沌はここからだった。曾禰は、これから起こりうるであろう、あらゆる混乱を予測し、矢継ぎ早に議場に問いを投げかけ、ルールをその場で作っていくという離れ業を演じなければならなかった。
第二幕:「私の眼と根性で認めました」
「次に申し上げたいことがあります」曾禰は、手元の資料に目を落としながら、さらに続けた。
「成立規則にも明文のない事柄があります。しかし、これを決めておかないと後々混乱を招きますので、あらかじめ皆様のご同意を得たい。投票用紙の中に、定められた定員より多く名前を書いたり、あるいは間違って一つの名前を重複して書いたりすることがないとは限りません。もし、定員より多く書いてあった場合、その定員を超過した名前は除外してしまいたい。これにご同意いただけますか」
再び末松謙澄が発言する。
「『除却する』とのことですが、それは単純に考えれば、リストの最後に書かれた名前を除外すると理解してよろしいか。場合によっては先頭を削るという規定を定めた場所もありますが、末尾を削るというご趣旨であれば、異存ありません」
「では、文章にして読み上げます」
と曾禰は応じた。
「『投票中、その選挙すべき定員より多く被選挙人の氏名を記載した時は、定員に超過した氏名の末尾よりこれを除却する』。これに不同意の方はいらっしゃいますか」
「よろしい!」
という声が場内から聞こえ、このルールも可決された。曾禰は次々と、起こりうるケースを潰していく。
「第二に、『投票に記載された氏名が選挙すべき定員に満たなくても、その記載された氏名は有効とする』。つまり、三人選ぶべきところを一人しか書かれていない票であっても、その一票は有効とする、ということです。これにご同意の方は?」
この提案に対し、今度は明確な反対意見が表明された。十七番、田中源太郎である。
「私は、それでは不都合が生じるかと思います。なぜなら、もし一人だけの記入を有効と認めてしまえば、三百人の議員がそれぞれ一人ずつ名前を書けば、三人の候補者を挙げることができなくなってしまう。現実にはそのようなことはないという憶測はできるかもしれませんが、理屈の上では三人の候補者を選ぶことができなくなる。ですから私は、一人しか書かなかった者、あるいは三人以上書いた者は、いずれもその票を棄却するのが良いと考えます。現実にはないと言っても、道理に反することはできないはずです。私はこれに不同意を唱えます!」
十二番の高木正年も「十七番に賛成いたします!」と続いた。
しかし、これに反論する者もいる。
「反対論には同意できない。原案通りで差し支えないはずだ!」
「そもそも、四人以上書いた場合は末尾を削ると決まったばかりではないか。話を蒸し返すのはいかがなものか!」
賛成と反対が入り乱れる。曾禰は、あくまで「討論なし」の原則を貫こうとする。
「賛成者も、不同意者もいらっしゃいますが、先ほど申し上げた通り、本日は討論はいたしません。皆様それぞれのお考えで、起立にて決を採るより他に方法はないと考えます。では、もう一度、本席より提出した案を読み上げます。『投票に記載された氏名が選挙すべき数に満たなくても、その記載された氏名を有効とする』。これにご同意の方は、ご起立!」
結果は、またしても多数の起立。曾禰は、次々とルールを確定させていく。
「多数ですので、そのように決します」
「第三に、『投票に同じ氏名を重複して記載したものは、その一つを有効とし、その他は得票数に算入しない』」
「異議なし!」という声が飛び、これも可決。
「第四に、『氏名に誤字があっても、明らかに誰であるかを認められるものは有効とする』」
これも異議なく可決。
「なお、得票数が同数だった場合は、年長者を当選とすることで決したく存じます」
この提案に、またしても議場がざわついた。
「ただ今の件、私にはよく分かりませんでした」と末松謙澄が問う。
「同数者が出た場合です」と曾禰は説明する。
「例えば、決選投票で上位六人を選ぼうとした時に、七人、八人が同数だった場合、その中から年長者を採るということです」
これに対し、五十八番の加藤勝彌が異を唱える。
「年長者を採るというのは承服できない! 抽選で決めるべきだ!」
「五十八番に同意!」
ここで、二十七番の東尾平太郎が「その件は、すでに成立規則に定めがあるはずだ。わざわざここで議論するには及ばないと思うが」と指摘する。曾禰は補足した。
「ご注意申し上げます。規則にあるのは、過半数を得た者の中に同数者がいた場合の話です。私が今申し上げているのは、決選投票に進む者を選ぶ段階で、まだ誰も過半数を得ていない状況で同数者が出た場合のことです。ですから、抽選で採るか、年長者を採るか、この二つに決めざるを得ません」
「採決、採決!」の声が飛び交う中、「私は年長者を採ることに賛成します」という声も上がる。
「では、起立を求めます! 同数の場合は年長者を採る、ということにご同意の方はご起立!」
多数が起立した。
「多数ですので、そのように決します」
しかし、この判定に納得しない者がいた。百八十二番、鳥海時雨郎である。
「議長! ただ今、起立しなかった者がかなり多かったように見えましたが、何をもって多数と認められたのですか!」
この痛烈な問いに、追い詰められた曾禰書記官長から、この日の混乱を象徴する歴史的な一言が飛び出した。
「私ノ眼ト根性デ認メマシタ(私の眼と根性で認めました)」
議場は爆笑に包まれた。「無用、無用! 時間の無駄だ!」というヤジも飛ぶ。ルールなき議会を手探りで運営する現場の苦悩と、それを笑い飛ばすしかない議員たちの姿がそこにはあった。
この後も、小西甚之助が「もし同数者が生年月日も同じだったらどうするのか」という、さらに細かい点を指摘し、結局「その場合は抽選とする」というルールが追加されるなど、微に入り細を穿つ手続き論が続いた。こうして、一つ一つルールをその場で作るという、前代未聞のプロセスは、まだ終わらなかった。
第三幕:噴出する「議員の権利」― 選挙は始まらない
議長選挙の投票が始まる直前、事態は新たな局面を迎える。末松三郎と井上角五郎が、相次いで「選挙とは別の、議員の権利に関わる重大な発言をしたい」と許可を求めたのだ。
「選挙の前に、議員の権利に関わることについて発言し、諸君の賛成を得たい!」
末松三郎が鋭い口調で要求する。しかし、暫定議長の曾禰は、あくまで選挙を優先させようと、これを制止した。
「ただ今は選挙だけのことです。選挙に関わることならともかく、その他の事柄であれば、議長選挙が終わった後にご意見を提出されるのが筋かと思います」
「いや、選挙を行う前にこそ、発言を許されることを議場に請求します!」
末松は一歩も引かない。
曾禰は困惑しながらも、自らの方針を貫こうとする。
「本日、私が議長の職務を行うにあたっては、選挙に直接関係のない発言は一切お止めいただく所存です」
この曾禰の言葉に、末松は激高した。
「書記官長に、議員の発言を中止させる権限があるというのか! それをこそ、この議会に問うてみたい! これは我々、議院の権利に関わる問題だ!」
議場は騒然となる。
「発言を止めさせるのか、させないのか、今すぐ議会に問うてもらいたい!」
と末松は食い下がる。
追い詰められた曾禰は、再び起立採決に訴えた。
「……では、諸君に起立を求めます。選挙に直接関係のない事柄については、発言を許さない、という私の意見に同意の方はご起立を!」
結果は、多数の起立。末松の発言は封じられた。
しかし、これで終わらない。今度は井上角五郎が立ち上がった。
「私も、この場で是非とも発言を請わねばならないことがある! このことは、たとえ選挙が終わった後であろうと我々が提出する議論であり、皆様のお耳に入れておかなければ、せっかくの選挙も無効になるだろうと思われる事柄だ! 発言の上、意見を述べさせていただきたい!」
井上のただならぬ気迫に、議場は再び緊張に包まれる。だが、その井上の発言を遮るように、今度は理論家の末松謙澄が、別の角度から問題を提起した。
「皆様の権利問題も重要ですが、その前に、私は議長選挙そのもののルールに、まだ決まっていない重大な問題があると考えます。そちらを先に定めるべきです」
末松謙澄が指摘したのは、投票ルールの根本的な欠陥だった。
「現行の規則では、最初の投票で過半数を得る者が、当選者数の三人を超える可能性があります。例えば、全議員が三票ずつ投じ、百八十票を得た者が五人出た場合、全員が過半数を超えてしまう。そうなった場合、誰を当選者とするのか、規則には何も書かれていない。また、決選投票で過半数を得る者が一人も出ない、という事態も十分に考えられる。そうなった場合、どうするのか。これも決まっていない。このような不備を放置したまま選挙を行えば、必ずや後で大論争が起きるでしょう!」
そして末松は、具体的な補足規則案を提示した。それは、過半数を得た者が定数より多い場合は得票数の多い順に当選とし、決選投票で過半数を得る者が定数に満たない場合も、同様に得票数の多い者を当選者とする、という極めて現実的な内容だった。
「この条文を加えなければ、選挙は必ず行き詰まる! 是非ともご賛同願いたい!」
今井磯一郎も「全く同感だ! これを定めなければ、実際に支障が出ることは当然だ!」と強く賛同した。しかし、暫定議長の曾禰は、この提案に首を縦に振らなかった。
「議員諸君に申します。ただ今のこの場で、直ちに成立規則を変更するようなことはできません。補足することはできても、変更はできないと、私は固く信じております。ご提案の件ですが、もし同点者が出た場合は、その同点者で再度、決選投票を行う。それでも決まらなければ、再三再四、投票を行うしかない。本日は、そのお覚悟で投票していただきたい。今この場で、成立規則を変更することはできません!」
<詳細解説:なぜ規則を変更できなかったのか>
曾禰が「規則の変更はできない」と主張した背景には、この「成立規則」が勅令、すなわち天皇の命令という形で定められていたことがある。まだ正式な議長も決まっていない「成立前」の議会が、勅令をその場の議決で変更することは、手続き上も、また天皇への敬意の点からも、極めて困難であると彼は判断したのだ。この「勅令の壁」が、議会の自由なルール作りを阻み、後の更なる混乱の遠因となる。
曾禰が末松謙澄の動議を退けた、まさにその時、先ほど発言を求め、止められていた井上角五郎が、しびれを切らしたように叫んだ。
「議長! 私が要求した発言はどうなったのですか!」
「どのようなご発言ですか。選挙に直接関係することであれば…」
「直接関係します!」
井上は、強い口調で言い切った。
「では、発言を許します。ただし、本席において無用と認めた場合は、直ちに発言を中止させ、議員諸君のご意見を伺う他ありません」
曾禰は、そう釘を刺すことを忘れなかった。許可を得た井上は、ついに、この日の議場に最初の爆弾を投下する。
「発言いたします! この憲法の第五十三条に、『両議院の議員は現行犯罪または内乱外患に関する罪を除くほか、会期中その院の許諾なくして逮捕されることなし』という明文がございます。しかるに、本日この会において、十番議員、森時之助君は…!」
その名前が出た瞬間、曾禰は鋭く井上の言葉を遮った。
「二百三十番(井上議員)! それは選挙に直接の関係にあらず!」
「直接関係いたします!」
「憲法問題であり、選挙に直接の関係はない!」
「いや、直接関係がある! 関係があるという所以は…!」
二人の応酬で、議場は騒然となる。曾禰は、これ以上の議論は混乱を招くだけだと判断し、強硬手段に出た。
「…諸君に問います! ただ今、二百三十番より憲法問題が出ております。本席においては、今日ただ今の所では必要ないと認めますが、諸君のご意見はいかがでありますか!」
場内から「異議なし!」という声が多数上がる。
「では、本席の申すところにご同意の諸君は、ご起立!」
圧倒的多数が起立した。
「かくの如く多数でありますので、その通りに決定いたします!」
こうして、井上が提起しようとした「逮捕された議員」の問題、すなわち議会の根幹に関わる憲法問題は、暫定議長と多数の議員の判断によって、議論されることすらなく封殺された。しかし、この時封じ込められた問題は、決して消え去ったわけではなかった。それは、議会の水面下でマグマのように熱を溜め込み、数日後、より大きな形で噴出することになる。
数々の動議と紛糾の末、ようやく議場は静けさを取り戻し、曾禰書記官長は投票箱が空であることを議員たちに示し、静かに宣言した。
「これより、点呼を開始いたします」
時計の針は、すでに正午を大きく回っていた。
前代未聞の議長選挙は、まだその第一ラウンドが始まったばかりだったのである。
第二章:終わらない選挙 ― 投票地獄と白紙の抵抗(明治23年11月25日)
第一幕:第一回投票、そして誰もいなくなった
正午過ぎ。数時間に及ぶ手続き論争の末、ようやく第一回帝国議会衆議院議長選挙の投票が始まった。書記官が、各府県の着席順に従い、一人、また一人と議員の名前を厳かに読み上げていく。
「楠本正隆君」「谷元道之君」「風間信吉君」…
羽織袴の議員たちが、緊張した面持ちで自席を立ち、演壇へと向かう。彼らは、自らが選ぶべき三人の議長候補の名を記した投票用紙を、静かに投票箱へと投じていく。そして、もう一つの箱、名刺箱に自らの名刺を入れる。これが、誰が投票したかを証明する唯一の手段だった。
点呼は延々と続いた。三百名近い議員が一人ずつ投票する様は、壮観であると同時に、ひどく時間のかかる作業だった。議場には、単調な点呼の声と、議員たちの衣擦れの音だけが響いていた。
長い点呼が終わり、投票が締め切られたのは、それから一時間以上が経過した後のことだった。書記官長であり暫定議長の曾禰荒助は、開票を前に、一つの「事故」を報告しなければならなかった。
「皆様にご報告いたします。ただ今の投票において、末廣重恭君が誤って、名刺を投票用紙の箱の中へ一枚入れられました。つきましては、開票前にこの名刺だけを取り除くことを、皆様にお諮りいたします。ご異議がなければ、そのようにいたします」
議場から異議はなかった。末廣の名刺は、名刺箱へと移された。ささいなミスではあったが、ルールなき議会では、このような細かなこと一つ一つに全体の承認を得る必要があった。
いよいよ開票である
しかし、ここでまたしても「待った」がかかった。
八十七番、板倉中である。
「投票の開札について一言申し上げたい! 開札にあたっては、一同の疑念をなくし、公平を保つため、万が一の間違いもないとは信用しておりますが、念のため、議員の中から七名ほどを議長が指名し、開票に立ち会わせるようにしてはいかがか!」
この提案は、開票作業そのものへの不信感というよりは、今後の議会運営の公正さを担保するための「前例」を作りたいという意思の表れだった。曾禰はこれを受け入れ、議場に諮った。
「ただ今、板倉君より、開票作業に監視役を置いてはどうかとのご意見ですが、いかがいたしましょうか」
すると、意外なところから反対意見が出た。百二十一番、早川龍介だ。
「議長のご指名となると、そこへ行って開票の間じゅう、ずっと立っていなければならないのですか?」
「無論、その通りです」と曾禰。
「私は、別に疑いなどありませんから、そこまでするには及ばないかと思いますが」
「見たい」という意見と、「見るに及ばない」という意見。曾禰は、またしても起立採決で決着をつけようとした。
「では、お諮りします。三名ないし五名を本席より指名し、開票に立ち会わせるのが良い、というご意見に同意の方は、ご起立を!」
しかし、立ち上がったのは、ごく少数だった。「少数でありますので、この動議は消滅いたします」と曾禰は宣言し、ようやく開票作業へと移ることができた。
書記官が、投票用紙と名刺の数を数え上げる。
「ご報告します! 本日の投票者総数は二百九十二名。名刺の数と一致しております。よって、当選に必要な過半数は、百四十七票となります!」
曾禰の言葉に、議場は静まり返った。書記官が、一枚、また一枚と、投票用紙に書かれた名前を厳かに読み上げていく。議員たちは固唾をのんで、その声に耳を澄ませた。長い開票作業が終わり、集計結果が曾禰の元に届けられた。彼は、沈痛な面持ちで立ち上がり、議場に向かってゆっくりと口を開いた。
「諸君に、選挙の結果をご報告いたします」
議員たちの視線が、一点に集中する。
「中島信行君、百三十四票」
ざわっ、と議場が揺れた。最大得票者ですら、過半数に13票も足りない。
「以下、津田眞道君、百十一票。河野廣中君、百二票。楠本正隆君、八十四票。芳野世經君、八十一票。松田正久君、六十六票。……全員、過半数に達しておりません。よって、改めて決選投票を行わなければならない事態となりました」
議場に、深い、深いため息が漏れた。その他にも、島田三郎君が五十七票、大江卓君が四十一点、藤田茂吉君が三十九点と、数多の議員に票が分散していた。ここに、派閥が乱立し、確固たる多数派が存在しない、第一回議会の現実が残酷なまでに露呈したのだ。
<詳細解説:なぜ誰も過半数を取れなかったのか>
この結果は、当時の政界の構図を如実に物語っている。この議会には、大きく分けて政府寄りの「吏党(りとう)」と、反政府色の強い「民党(みんとう)」が存在した。しかし、民党も一枚岩ではなく、板垣退助率いる旧自由党系の「自由党」、大隈重信率いる旧改進党系の「改進党」など、複数のグループに分かれていた。そのため、どの候補者も単独で過半数を獲得することが極めて困難だったのである。この構造的な問題が、この後の「投票地獄」を生み出すことになる。
曾禰は、淡々と手続きを進めた。
「決選投票を行うにあたり、成立規則第八条に基づき、ただ今申し上げた得票数上位の六名を候補者といたします。すなわち、中島信行君、津田眞道君、河野廣中君、楠本正隆君、芳野世經君、松田正久君。この六名の中から、改めてご投票をお願いいたします。六名以外の方の名前を書かれた票は、無論、無効といたします」
書記官たちが、再び慌ただしく投票用紙を配り始める。時刻はすでに昼を大きく過ぎている。ここで、六十九番の天野三郎が声を上げた。
「すでに十二時も過ぎました! 食事を摂ってからにしてはいかがか! 満場のご賛成を得たい!」
しかし、この提案は、百七番の櫻井徳太郎によって即座に打ち消された。
「いや! 直ちに決行することを希望します!」
「食事は後にして、投票を決行されるよう希望します!」
議場も「直ちに決行すべし!」という声が多数を占めた。
「では、直ちに続行いたします!」
曾禰の宣言とともに、二度目の点呼が始まった。
第二幕:二人の当選者と、残る一つの椅子
二度目の投票は、一度目よりも少し早く進んだ。議員たちの間にも、若干の疲労と焦りの色が見え始めていた。投票が締め切られ、再び開票作業が行われる。今度こそ決まるのか。議員たちの期待と不安が入り混じる中、曾禰が再び報告のために立ち上がった。
「投票の結果を報告いたします! 得票数は、中島信行君、百六十一票。津田眞道君、百五十八票。…」
おおっ、と議場がどよめいた。二人とも、過半数の147票を大きく超えている。
「…松田正久君、百四十一票。楠本正隆君、百三十八票。河野廣中君、百二十三票。芳野世經君、百一点」
曾禰は、一呼吸置いて、結果をまとめた。
「選挙の結果は、ただ今の通りでありまして、中島信行君と津田眞道君が、過半数の投票を得られました。よって、このお二方は当選人であります!」
議場から、まばらな拍手が起こった。ようやく、三人の議長候補のうち、二人が決まったのだ。しかし、問題は残された一つの椅子だった。
「…しかしながら、三人を選ぶべきところ、当選者はまだ二人であります。あとお一人が決まっておりませんので、これより、さらに決選投票を行わなければなりません」
議場に、またしても疲労のため息が広がった。
「つきましては、残る候補者の中から得票数の多かったお二人、すなわち、松田正久君と楠本正隆君。このお二人について、今から決選投票を行っていただきたく存じます。方法は、全てこれまでと同様です」
書記官たちが、三度目の投票用紙を配り始める。演壇には、当選した中島、津田両名の名と、決選投票に臨む松田、楠本両名の名が掲げられた。議員たちは、もはや機械的に、三度目の投票へと向かっていった。
三度目の投票が終わり、開票が始まる。谷元道之君が、またも名刺を投票箱に入れてしまうという小さなハプニングはあったが、手続きは粛々と進められた。そして、ついに最後の結果が告げられる。
「ただ今の投票の結果を、ご報告いたします!」
曾禰の声が、静まり返った議場に響いた。
「松田正久君の得票、百五十二票! 過半数であります!」
おお、という歓声とも安堵の声ともつかない声が上がった。
「楠本正隆君、百三十四票!……よって、松田正久君が当選と決まりました!」
ついに、三人の議長候補者が決定した。中島信行、津田眞道、松田正久。この三名の名が天皇に奏上され、その中から初代議長が任命されることになる。
「これで、議長選挙は完結いたしました。この結果をもって、上奏いたします」
曾禰は、安堵の表情を浮かべながら宣言した。
しかし、安堵したのも束の間だった。
「これから、引き続き、副議長選挙に取り掛かります!」
曾禰の非情な宣告に、議場は深い疲労感に包まれた。まだ、この長い一日は終わらないのだ。
第三幕:白紙の抵抗と、終わらない投票
副議長選挙は、議長選挙で繰り返された混沌を、さらに凝縮したような様相を呈した。投票と開票が繰り返されるが、一向に過半数を得る者は現れない。
芳野世經、河野廣中、島田三郎、楠本正隆、松田正久、津田眞道。有力候補者たちの間で票は割れ、誰も決定打を放てないまま、時間だけが過ぎていく。
そんな中、一つの事件が起こる。決選投票の候補者の一人となった島田三郎が、演壇に向かって驚くべき発言をしたのだ。
「三十番、島田三郎です! 私は、これ以上決選投票で皆様のお手を煩わせるまでもないと存じますので、この選挙を辞退することを明言しておきます! 万一、この上で私が多数の票を得たとしても、辞退するつもりですので、どうか次点の方へお回し下さることを望みます!」
これは、膠着した状況を打開するための、島田なりの配慮だった。自分が身を引けば、他の候補者に票が集中し、決着がつくだろうと考えたのだ。しかし、この「選挙前の辞退宣言」が、議会に新たな混乱の火種を投下する。
「無用だ!」と叫ぶ議員が現れる。
「そのような前言は無用である!」
「議長! 本席の申すことが無用だというのか!」
曾禰は、島田の申し出をどう扱うべきか、判断に窮した。
「もし、このような『当選しても辞退する』ということがまかり通れば、選挙は永遠に終わらなくなってしまいます。夜が明けても、当選者を決めることができなくなる。後のためにもなりますので、ここは議会の皆様のご判断を仰ぎたい」
しかし、島田も譲らない。
「私が辞退すると申し上げたのは、皆様の貴重な投票と貴重な時間を空費するのを惜しんだためです。しかし、当選しても辞退するという意思は固いので、そのことをあらかじめお断りしておけば、私の心としては何ら差し支えないと考えます」
結局、曾禰は「選挙結果が出てからでないと、そのようなことは扱えない」として、島田を含めた六名での決選投票を強行した。
だが、その結果は、またしても「当選者なし」だった。
誰も過半数を獲得できない。まさに、末松謙澄が選挙前に危惧した通りの事態が、現実のものとなったのだ。議場は、出口のない迷宮に迷い込んだかのような、重苦しい空気に包まれた。
ここで、六番の高梨哲四郎が、現状を打破するための大胆な提案を行う。
「すでに決選投票を行ってもなお、結果を得られないのであれば、これ以上再三繰り返すのは無益であると考えます! ここは、衆議院成立規則第十二条『選挙につき疑義を生じたるときは書記官長は集合したる議員に諮りこれを決すべし』という条文を適用し、ただ今の決選投票における最多得票者から順に三名を当選者として、天皇に上奏することを希望します!」
これは、事実上「過半数」という原則を放棄し、「多数決」で決着をつけようという提案だった。しかし、これに法律家の岡山兼吉が猛然と反対する。
「再三投票することが無益であるのは、高梨君の言う通りだ! しかしながら、多数決で決するということは、勅令をもって定められている『過-半数』の規則に明らかに背くことになる! そのようなことは、到底できるものではない! 結局のところ、勅令そのものを修正していただくよう上奏するか、何か別の方法を考えるしかない。勅令がある以上、それに背いて多数決で決することには、断固として不同意である!」
「多数決」か、「過半数」か。
「議会の円滑な運営」か、「法(勅令)の厳格な遵守」か。
二つの正義が、議場で激しく衝突した。
「勅令を修正するなど、時間がかかりすぎる! 速やかに決選投票を執行されたい!」
「いや、そもそも白紙票を入れる者がいるのが問題だ! その者たちは欠席者と見なすべきではないか!」
「もう一度やれば、今度こそ譲り合いで決まるだろう!」
「いや、30分休憩して、頭を冷やすべきだ!」
怒号とヤジが飛び交い、議論は完全に紛糾した。曾禰は、この混乱を収めるため、休憩を提案する。
「…十五分ほど休憩して、皆様、頭を冷やされてはいかがか…」
この一言が、新たな火種を生んだ。百二番、田中正造が激高して詰め寄る。
「議長! ただ今、『頭を冷やす』とおっしゃったが、それはどういう意味か!」
「いや、何、私の頭もだいぶのぼせておりますし…」
「なぜ、そのような軽々しい言葉を用い、議員を侮辱するのか!」
「決して侮辱などでは…私の言葉が悪かったのであれば、甚だ気の毒千万であります…」
曾禰が謝罪するも、議場の混乱は収まらない。もはや、議論の本質から離れ、感情的な対立が支配し始めていた。この泥沼のような状況を打開するため、ついに末松謙澄が、選挙前に一度は退けられた、あの動議を再び提出する。
「何度も決選投票を繰り返すなど、あってはならないことだ! 最初に私が述べたとおり、この際、規則を補う形で、『決選投票において過半数を得る者がいない場合は、得票数の多い者から順に当選者とする』というルールを、この場で議決しておくべきだ! これは勅令の修正ではない。定められていない部分を、我々議会が補うだけのことだ!」
この提案に対し、岡山兼吉が再び反論する。
「規則の精神は、あくまで過半数だ! それを補うなどということはできない! 我々は、成立規則に従って進退するより他に道はない!」
しかし、出口の見えない議論に疲れ果てた議場の空気は、明らかに末松の提案に傾きつつあった。曾禰は、ついに決断を下す。
「…では、お諮りします! もう一度、決選投票を行う。そして、それでもなお過半数を得る者がいない場合は、その投票における最多得…票者をもって当選者とする、という動議が出ております。これは、この次の投票を最終決戦とする、という意味です。これにご同意の方は、ご起立を!」
議場の大半が、堰を切ったように立ち上がった。
「多数! よって、そのように決します!」
曾禰は、力強く宣言した。
しかし、この決定は、新たな火種を生む。「勅令を議会の多数決で覆した」という、極めて重大な前例を作ってしまったからだ。田中源太郎らが「午前中は勅令だから変更できないと言っていたではないか! 議長の態度は矛盾している!」と激しく抗議し、堀内賢郎も「たとえ満場一致でも、勅令に背く決議には従えない!」と叫んだ。
議場は、賛成派と反対派が入り乱れ、再び収拾のつかない状態に陥った。もはや、何が議決され、何が否定されたのか、誰にも分からなくなっていた。
「議長! 決議の通り、速やかに投票を執行されたい!」
「いや、この決議は無効だ!」
曾禰は、混乱を断ち切るように叫んだ。
「どのようなご議論が出ようとも、一度議決した以上、その通りに執行いたします!」
この宣言を合図に、最後の決選投票が始まった。しかし、一部の議員は「勅令に背く投票はできない」として投票を棄権した。議場の混乱と分裂は、頂点に達していた。
開票作業中、書記官が、一枚の異様な投票用紙を読み上げた。そこには、こう書かれていた。
「笑フ可シ此議場、悲ム可シ此議長、恐ル可シ將來ノ會(笑うべきだ、この議場。悲しむべきだ、この議長。恐れるべきだ、将来の議会を)」
それは、この日の混乱を痛烈に皮肉った、名もなき議員の心の叫びだった。
投票の結果、またしても過半数を得る者は現れなかった。しかし、先ほど議決された「特別ルール」に基づき、この投票で最多得票を得た津田眞道、そして次点の楠本正隆、芳野世經が、副議長候補者として当選することが宣言された。
この時、すでに時刻は午後10時50分。
日本の議会史の最初の1ページは、前代未聞の混乱と、12時間を超える長時間の議論の末に、ようやく閉じられた。この日の出来事は、彼らがこれから歩む道のりの、あまりにも多難な序章に過ぎなかった。
第三章:天皇の言葉と議会の意志(明治23年11月29日)
第一幕:勅語、全文
議長選挙の混乱から4日後の11月29日。
第一回帝国議会は、荘厳な開会式を迎えた。明治天皇が臨席し、国民の代表として初めて集った議員たちに、直接、言葉を賜った。その一言一句は、これから始まる日本の議会政治が目指すべき道を示す、極めて重要なものであった。
【原文】
朕貴族院及衆議院の各員に告く
朕即位以來二十年間の經始する所内治諸般の制度粗粗其の綱領を舉けたり庶幾くは皇祖皇宗の遺徳に倚り卿等と倶に前を繼き後を啓き憲法の美果を收め以て將來に益益我か帝國の光烈と我か臣民の忠良にして勇進なる氣性とをして中外に表明ならしむることを得む
朕又夙に各國と盟好を修め通商を廣め國勢を振張せむことを期す幸に締約諸國の交際は益益親厚を加へたり
陸海の軍備は内外の平和を保全する爲に歳を積みて完實を期せさるへからす
明治二十四年度の豫算及各般法律案は朕之を國務大臣に命して議會の議に付せしむ朕は卿等か公平愼重以て審議協贊する所あることを期し併せて將來に繼くへきの模範を貽さむことを望む【現代語訳】
私は、貴族院と衆議院の各議員に告げる。
私が即位して以来二十数年、国内統治の様々な制度の骨格がようやく整った。願わくは、皇室の祖先の遺徳により、諸君らと共にこれまでの事業を受け継ぎ、未来を切り開き、憲法の素晴らしい成果を収めたい。そして将来、我が帝国の栄光と、忠実で勇敢な我が臣民の気性を、国の内外に示していきたいと思う。
私はまた、早くから各國と友好関係を結び、通商を広め、国力を発展させることを目指してきた。幸い、条約を結んでいる諸国との交際はますます親密さを増している。
陸海軍の軍備は、国内外の平和を保全するために、年月をかけて万全を期さなければならない。
明治二十四年度の予算および様々な法律案は、私が国務大臣に命じて議会の審議に付させるものである。私は、諸君らが公平かつ慎重に審議し、協力することを期待するとともに、あわせて将来に続くべき模範を残すことを望む。
この勅語は、単なる儀礼的な挨拶ではなかった。それは、新しく始まった議会に対する天皇の期待と、そして国家が直面する課題を明確に示した、政治的なメッセージであった。
初代議長に就任した中島信行は、この重い言葉を受け、議場に問うた。
「ただいまの勅語に対し、文書をもって奉答すべきでありましょうか、否か。皆様にお尋ねいたします」
第二幕:沈黙か、言葉か
この問いに、最初に口を開いたのは二百五十九番、河島醇だった。
「私は、勅語に対して奉答する必要はないと考えます。我々の本分は、公平慎重に審議協賛の職務を執行することであり、あえて言葉を飾って奉答する必要はありません。海外では奉答する例があると言う人もいますが、なぜ海外の例を引く必要がありましょうか。これは将来の儀礼にもなることです。言葉で奉答せず、謹んで勅語の精神を奉じ、議員としての職務を尽くすことが肝要であります」
沈黙と行動こそが最上の敬意である、という武士的な美学にも通じる、力強い意見だった。しかし、すぐさま二百三番の小西甚之助が反論に立つ。
「いや、私は議長のご報告に対し、意見を述べさせていただく。すなわち、勅語に対しては奉答するという意見であります! 天皇陛下は、本日、直々に貴族院に臨御され、我々に懇ろなるお言葉を賜りました。その精神を尋ねれば、『公平慎重に審議協賛せよ』ということであります。このように陛下が各議員に望んでおられる以上、我々議員もまた、『謹んで勅命を奉じ、公平慎重に審議協賛いたします』ということをお誓いするのが、勅語に対する礼儀というものでしょう。直々にお越しになってお言葉を賜ったのですから、文書をもって奉答することを、私は最も希望するものであります。そればかりか、議院法第五十一条に基づき、議長が宮中に参内し、陛下に謁見を請い、直接奉答することを、あわせて希望するものであります!」
奉答は不要とする「実」を取るか、必要とする「礼」を取るか。議会は、その基本的な姿勢から問われることになった。
「奉答ごときで、そこまで議論する必要はない!」
「討論は無用! 採決を!」
ヤジが飛び交い、議場は騒がしくなる。
「私は討論を尽くして決めたい!」という安田愉逸のような意見もあったが、大勢は即時採決に傾いていた。中島議長は、場の空気を読み、宣言した。
「だんだんとご意見も出ましたが、討論を用いずに採決を、というのが多数のようですので、これより決を採ります。勅語に対し、奉答すべし、と考える諸君はご起立!」
結果は、圧倒的多数の起立。ここに、衆議院は天皇に対し、その言葉で意志を返すことを決めた。
第三幕:誰が「議会の言葉」を紡ぐのか
奉答することが決まると、即座に次の問題が持ち上がった。「では、その奉答文は、誰が、どのようにして作るのか?」
議長選挙の混沌が、再び繰り返されようとしていた。
「奉答することが決まった以上、議長閣下よりご奉答なさるのが至当であると考えます!」と鳥海時雨郎が提案する。
しかし、大岡育造は「いや、委員を選んで起草させるべきだ!」と反論。
佐々木善右衛門も「委員を選ぶことに賛成する! 軽率に奉答案を議することはできない!」と続く。
「議長に起草していただくのがよかろう!」
「いや、それでは議会の総意とは言えん!」
「委員に全権を委任すべきだ!」
「いやいや、委員が作った草案を、再度この議場で審議すべきだ!」
またしても、手続きを巡って議場は紛糾する。一つのことを決めるのに、その方法で議論が紛糾し、一向に前に進まない。これが、第一回議会の日常となりつつあった。そんな中、百五番の末松謙澄が、一つの情報を議場にもたらした。
「色々ご意見がありますが、仄聞するところによれば、議長のお手元には、万一のために草案のようなものが準備されていると聞きました。もし、そのようなものがあるのでしたら、この場で一度読み上げていただき、それで良いか、あるいは不満足かを相談し、もし不満足であれば委員を選ぶ、という手続きにしてはいかがでしょうか」
この提案に、何人かが賛同の意を示す。しかし、「いや、何があるか分からぬが、とにかく委員五名を選んで起草させることを希望する!」(工藤行幹)、「何はなくとも、委員を選挙することが必要だ!」(今井磯一郎)という声も根強く、議論は平行線を辿った。
大江卓は、議長に一任することに強く反対した。
「議長に起草までお任せしておくわけにはいかない! 起草委員を選び、その委員が起草したものについて、我々の意向を討論し、衆議の決した上で奉答しなければならない!」
「こんなことに時間を費やすのは惜しい! 委員を選ぶかどうか、採決を!」
「そうだ! 喋々するのは好まない!」
ヤジと怒号が飛び交う中、中島議長は、まず委員を設けるか否かを決することにした。
「では、決を採ろうと思います。まず、委員を設けるや否やについて、決を採ります」
ここで、佐々木正蔵が鋭い質問を投げかける。
「委員を設けることには同意ですが、それは単なる『起草委員』なのか、それとも全権を委ねて、奉答文については二度とこの議場で議さない、ということなのか。その二点をはっきりさせてから、採決していただきたい」
「委員を設けることが決まってから、その後のやり方を決めようと思います」と中島議長は答え、採決を強行した。「委員を設けることに同意の方は、ご起立!」
多数が起立した。しかし、堀部勝四郎が「多数ではない!」と叫び、議場が紛糾したため、再度、反対者の起立を求めるという念の入れようで、ようやく「委員を設ける」ことが決定した。
次に、委員の人数を巡って議論が紛糾。「五名」「各部から一名ずつ九名」「議長指名」「投票で選ぶべき」といった意見が乱れ飛んだ末、これも採決となり、「各部から一名ずつ、計九名」と決まった。
しかし、議論はまだ終わらない。
「その九名の委員に、奉答文作成の全権を委任するのか? それとも、委員が作った草案を、もう一度この議場で議論するのか?」
この最終的な手続きを巡って、またしても賛否両論が渦巻いた。
中島議長は、この長引きそうな議論を断ち切るべく、最後の採決を促した。
「起草委員に、すべてを任せるというお考えの諸君はご起立!」
書記官が人数を数える。
「……百五十八名!」
多数により、奉答文の作成は、各部から選出される九名の委員に全権委任されることが、ついに決定した。
こうして、開会式の日の議事は、奉答文をどう作るかという手続き論に終始し、午後一時十七分、ようやく散会となった。彼らが一つ一つの手続きにこれほど時間をかけたのは、それがすべて、今後の議会運営の「前例」となるからであった。その一つ一つの積み重ねが、日本の議会制民主主義の歴史を形作っていくことになる。
第四章:白紙の乱 ― 終わらない選挙と、その場で変えられたルール(明治23年12月2日)
第一幕:名前か、番号か ― 議会の威厳を巡る小競り合い
議長選挙の大混乱から一週間後の12月2日、午後1時40分。ようやく初代議長として議長席に座った中島信行のもと、衆議院は議事進行の要となる「全院委員長」の選挙に臨んでいた。
中島議長は、前回の混乱を繰り返すまいと、手際よく議事を進めようとする。
「これより、全院委員長の選挙を行います。本日の点呼は、時間を短縮するため番号で行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。その他の手続きは、先日の議長・副議長選挙の例に倣って行うつもりです」
しかし、このささやかな効率化の提案に、すぐさま異議が唱えられた。百五十七番、大江卓が鋭い声で言った。
「議長! 我々には姓名がある以上、どうぞ番号でお呼びになるのはお止めいただきたい!」
議会人としての矜持が、番号で呼ばれることを許さないのだ。議場からは「そうだ、氏名を呼ぶべきだ!」という声と、「いや、番号で差し支えない!」という声が同時に上がり、またしても議事が停滞する。
「議論は不要!」「採決、採決!」というヤジが飛び交う。中島議長は、やむなく起立を求めた。
「では、お諮りします。番号で呼ぶことに差し支えない、という方はご起立!」
結果は、多数の起立。効率が、威厳に勝った瞬間だった。しかし、このささいなやり取りは、この議会が手続きの一つ一つ、言葉の一つ一つに、いかに敏感であったかを物語っていた。書記官が投票用紙を配り始め、議場は再び選挙の緊張感に包まれた。
第二幕:既視感(デジャブ)― 再びの投票地獄
投票が終わり、開票が始まった。その最中、二百十二番の松野新九郎が、ふと気づいたように議長に質問した。
「開票前に伺いたい。議長は投票されたようにお見受けできませんでしたが、議長も我々三百人の一人なれば、投票権があると考えます。いかがでしょうか」
百四十六番の早川龍介も続く。
「議長にもご投票を願いたい! これは、私が切に希望するところであります!」
この指摘を受け、中島議長は静かに席を立ち、自らの一票を投じた。これもまた、将来の議会運営の「前例」となる一幕だった。やがて、開票結果が報告された。しかし、その内容は、一週間前の悪夢の再来を告げるものだった。
「投票の結果を、ご報告申し上げます! 河野廣中君、百三十票。島田三郎君、百一点……何れも過半数に達しておりません!」
過半数である百四十七票には、誰も届かない。そして、議場をさらに深くため息させたのは、続く報告だった。
「……なお、無効の投票が、六票ございました」
前回あれほど問題になった無効票が、またしても投じられたのだ。上位二名、河野廣中と島田三郎による決選投票が決まったが、議員たちの間には、このままではまた同じことの繰り返しになるのではないか、という重苦しい空気が漂い始めていた。
第三幕:「有効投票」とは何か ― ルールの欠陥を巡る大論争
決選投票を前に、百六十四番の浅野順平が、この選挙制度の根本的な欠陥を鋭く突いた。
「議長に質したい! これまでの選挙では、白紙や悪戯書きのような無効票も、すべて投票総数に加えられてきました。これでは、無効票を投じる者がいる限り、永遠に過半数に達しないという事態も起こりうる! 決選投票における『投票の過半数』とは、無効票を除いた『有効投票の過半数』と解釈すべきではないのか! この点を、はっきりさせていただきたい!」
的を射た指摘だった。これまで曖昧にされてきた「投票総数」の定義が、今まさに議会の前に突きつけられたのだ。議場は「そうだ、その通りだ!」という賛同の声で満ち溢れた。
しかし、この流れに待ったをかけたのが、ケンブリッジ帰りの論客、百五番の末松謙澄だった。
「そのお考えには私も大いに賛成でありますが、しかし、それは昨日議決したばかりの衆議院規則に抵触しないでしょうか?」
末松は、静かに、しかし論理的に語り始めた。
「規則第七条には、ただ『投票ノ過半数ヲ得タル者ヲ以テ当選人トス』とあるのみ。『有効』という文字はございません。西洋の法律では『有効』の文字が入っておりますが、我が国の規則にはない。この規則文を我々がその場の都合で解釈してよいものでしょうか。一度決めた規則を安易に変えることは、法の安定性を損なうのではないかと危惧いたします。規則の条文には、書かれていない以上の意味はないと見るべきです。もちろん、私も心情的には有効票のみで計算すべきだと考えますが、この規則との矛盾という困難を、いかにすべきか。皆様のお考えを伺いたい」
浅野の提起は、議事の円滑化という「実利」を求めるもの。末松の反論は、一度決めたルールは守るべきだという「原則」を重んじるもの。議会はまたしても、根本的な問題に突き当たった。
中島議長は、この問題を議場に諮った。
「では、決を採ろうと思います。百三十九番、清水君の建議、すなわち『有効投票の過半数』と決することに、ご同意の方はご起立!」
結果は、少数の起立。この時点では、規則の厳格な運用を求める声、すなわち末松の指摘した「原則」が上回った。決選投票は、これまで通り、無効票もすべて含めた総数の過半数で争われることになった。
第四幕:禁じ手 ― ルールは、その場で変えるためにある
そして、決選投票が行われた。候補者は河野廣中と島田三郎の二人。議場は、今度こそ決着がつくであろうという期待と、またしても同じ結果になるのではないかという不安が入り混じった、異様な緊張感に包まれていた。
開票結果が告げられる。
「投票の結果を、ご報告いたします! 河野君、百四十三票! 島田君、百四十一票!」
どちらも、過半数の百四十七票に届かない。
「……無効の投票が四枚、白紙が五枚ございます」
議場は、騒然となった。というより、もはや怒りと失笑が入り混じったような空気が支配していた。
「これでは埒が明かん!」
「また投票か!」
「白紙を入れる不届き者がいる限り、同じことの繰り返しだ!」
中島議長は、やりきれないといった表情で議員たちに訴えかけた。
「どうか、謹んで諸君に申します。この議会を重んずるがために、どうか、謹んで投票を行っていただきたい。白紙を投じるがごときは、いかにもこの議会のためになりませぬ…」
この完全な行き詰まりを前に、十二番の堀内忠司が叫んだ。
「こうなった以上、次の決選投票で、たとえ過半数に達しなくとも、多数を得た者をもって当選と決すること満場に建議いたします!」
工藤行幹も続く。
「そうだ! この中に、白紙を入れるような不届きな者がいるのだ! そんな者がいる限り、いつまでやっても過半数を得るわけがない! この上は多数をもって決せられることを切望する!」
しかし、それは規則違反だ。議会は、自らが作った規則の壁によって、完全に身動きが取れなくなってしまった。
この膠着状態を打ち破るべく、二百六十二番の末廣重恭が、前代未聞の動議を提出する。それは、この場で行き詰まりの原因となっている衆議院規則第三十条そのものを、今この場で「修正」してしまおうという、まさに禁じ手とも言える提案だった。
【末廣重恭による修正動議案】
衆議院規則第三十条の次に、以下の一項を加える。
「決選投票ヲナシ過半数ヲ得タル者ナキトキハ再ヒ決選投票ヲ行ヒ最大多數ヲ得ル者ヲ以テ當選人トナス」【現代語訳】
「決選投票を行っても過半数を得た者がいない時は、もう一度決選投票を行い、その投票で最も多くの票を得た者を当選者とする」
これは、過半数の原則を事実上、放棄するものだった。しかし、この混乱を収拾するには、もはやこれしかない、という空気が議場を支配しつつあった。
さらに、この修正案に対し、末松謙澄が「修正の修正」を提出する。
「いや、それではまだ甘い! 再び決選投票を行う必要はない!」
【末松謙澄による修正の修正案】
衆議院規則第三十条を以下のように修正する。
「(決選投票ヲ)行ヒ、多數ヲ得タル者ヲ以テ當選人トス」【現代語訳】
「(決選投票を)行い、多くの票を得た者を当選者とする」
末松の案は、再度の決選投票すら不要とし、一回の決選投票で多数を得た者を当選者とする、より大胆なものだった。彼は、議長選挙の例に倣うべきだと主張した。
議事日程の緊急変更という手続きを経て、この二重の修正案が採決にかけられる。
「末松君の修正の修正に、ご同意の方は、ご起立!」
議場の大半が、堰を切ったように立ち上がった。多数決により、規則は即日修正された。行き詰まりを打開するため、彼らは自ら作ったルールを、その場で自ら書き換えるという荒業をやってのけたのだ。
第五幕:新ルールの下で
こうして、全く新しいルールの下、三度目の決選投票が行われることになった。候補者は、変わらず河野廣中と島田三郎。もはや、過半数という呪縛から解き放たれた議員たちの投票は、ある種の晴れやかさすら帯びていた。
投票が終わり、開票される。
結果は、中島議長によって高らかに告げられた。
「投票の結果を、ご報告申し上げます! 島田三郎君、百四十九票! 河野廣中君、百三十六票! よって、多数を得られました、島田三郎君が当選と相成りました!」
議場から、今度こそ万雷の拍手が湧き起こった。
午後7時55分、退場。この日の議会は、行き詰まりを打開するために、その場でルール自体を作り変えるという、荒々しいが力強い生命力を示した。それは、まだ固まりきっていない、黎明期の議会だからこそ可能な、荒業であった。
第五章:消えた議員 ― 憲法第53条を巡る攻防(明治23年12月4日)
第一幕:一件の動議と、一枚の通知書
12月4日、午後1時55分。議会が始まって一週間以上が経過し、ようやく本格的な議論が始まろうとしていた。その日の議事日程の第一番には、こう記されていた。
「衆議院議員にして會期前に逮捕せられ開會の後尚ほ拘留中の者に係る件(末松三郎君動議)」
これは、東京府選出の議員、森時之助に関する問題だった。彼は、議会が開かれる前に「委託物費消(横領)」の容疑で逮捕され、議会が始まった後も、なお拘留され続けていたのだ。
議事が始まるにあたり、中島議長はいくつかの報告を行った。その最後に、彼はこう付け加えた。
「…なお、拘留のために本日出席されていない議員は、森時之助君であります」
この言葉を受け、百十二番の末松三郎がすっくと立ち上がった。
「ただ今、森時之助君が拘留中であるとのことですが、それについては司法大臣からの通知があったと承知しております。つきましては、その通知書の朗読を請求いたします」
中島議長は頷き、書記官長に朗読を命じた。曾禰書記官長が、厳かな口調で読み上げる。
【司法大臣からの通知書(11月24日付)】
【原文】「衆議院議員當選者森時之助ハ當今委托物費消破〓事件ニ付東京地方裁判所ニ於テ審問拘留中ニ有之候依ッテ此段及通知候也 明治二十三年十一月二十四日 司法大臣伯爵山田顯義 衆議院書記官長曾禰荒助殿」【現代語訳】
「衆議院議員当選者である森時之助は、現在、委託物横領事件について東京地方裁判所において審問中で、拘留されています。よって、この旨を通知いたします。明治二十三年十一月二十四日 司法大臣伯爵 山田顕義 衆議院書記官長 曾禰荒助殿」
この通知書は、議会が始まる前日に、書記官長宛てに送られていたものだった。この一枚の紙が、これから始まる大論争の引き金となる。
第二幕:議会の権利か、司法の独立か
議事日程に従い、動議者である末松三郎が静かに演壇に登った。彼は、この問題を選挙中の25日から提起しようと試みてきたが、議事の混乱を理由に、何度も発言を止められてきた。そして今日、ようやくその機会を得たのだ。
末松はまず、自らが提出した動議案を朗々と読み上げた。
【末松三郎による動議案】
【原文】「衆議院議員ニシテ開期前ニ逮捕セラレ開會後尙拘留中ノ者ハ、衆議院ノ許可アルニ非サレハ引續キ拘留スルコトヲ得ズ」【現代語訳】
「衆議院議員であって、会期前に逮捕され、開会後もなお拘留されている者は、衆議院の許可がなければ、引き続いて拘留することはできない」
読み終えた末松は、静まり返る議場に向かって、その真意を熱を込めて語り始めた。
「諸君も御存知の通り、大日本帝国憲法第五十三条には『両議院の議員は現行犯罪または内乱外患に関する罪を除くほか、会期中その院の許諾なくして逮捕されることなし』とあります」
<詳細解説:憲法第五十三条>
これは、議員の「不逮捕特権」を定めた条文である。政府の不当な弾圧から議員の身分を守り、議会の独立性を確保するための、極めて重要な規定だった。
「この憲法の精神は、議会の独立を保ち、我々の議事を妨げさせないようにすることにあるはずです。もし、政府がその気になれば、会期の直前に、政府に批判的な有力議員を何かの口実で逮捕し、議会が終わるまで拘留し続けることも可能になってしまう。それでは、この第五十三条は意味をなしません! 会期前に逮捕された者であっても、会期が始まった以上、その身柄の拘束を続けるには、我々衆議院の『許諾』が必要であると解釈するのが、憲法の精神に合致するはずです。これは、森時之助氏個人の問題ではない。我々衆議院全体の、そして未来永劫に続く帝国議会の権利に関わる重大な問題なのです!」
末松の熱のこもった演説に、議場は水を打ったように静まりかえった。彼の論理は明快であり、議会の尊厳を守ろうとする気概に満ちていた。しかし、この動議に、二人の論客が待ったをかけた。一人は、法律家の岡山兼吉だった。
「末松君の言う、憲法の精神には、私も全く同感だ。議会の権利は守らねばならない。しかし!」岡山は一呼吸置いて続けた。「しかし、我々はこの数日間、何をしていたのか? 11月25日の議長選挙の日に、井上角五郎君や末松君がこの問題を提起しようとしたのを、我々多数は『選挙に直接関係ない』として、その発言を封じてしまった。森議員が拘留されている事実を知りながら、この問題を今日まで放置してきたではないか。それは、議会が森議員の拘留を『默諾(もくだく)』、つまり暗黙のうちに承認していたことに他ならない! 今更この動議を議決して、司法の判断に介入しようとすれば、裁判所から反発を招き、貴族院とも対立し、最終的に我々の権利が認められなかった場合、議会は永遠にこの貴重な権利を失うことになる。それは、万々歳まで消えることのない不名誉だ! 私は、議会の権利を失うことを恐れるが故に、あえてこの動議に反対する!」
これは、理想よりも現実的なリスクを重んじる、老練な法律家ならではの議論だった。続いて、大岡育造が、より直接的な反論を展開した。
「末松君は、フランスやプロイセンなど、外国の例をやたらに引用するが、ここは日本帝国議会である! 日本の憲法を、外国の物差しで測るべきではない! 憲法第五十三条の条文を素直に読めば、『会期中』と明確に書かれている。会期前の逮捕にまで、この条文が及ぶと解釈するのは、あまりに拡大解釈だ。また、この条文には『内乱外患に関する罪を除く』とある。もし政府が悪意を持つなら、わざわざ面倒なことをせずとも、議員に内乱罪のレッテルを貼って逮捕すればよいではないか。我々が信頼すべきは、条文の拡大解釈ではなく、司法権の独立である。この動議は、議会の権利を守るように見えて、司法権の独立を侵害する危険なものだ!」
議会の権利か、司法権の独立か。憲法の精神か、条文の厳格な解釈か。議論は、近代国家の根幹を揺るがすテーマへと発展していく。
賛成派の井上角五郎は、「岡山君の言う『黙諾』など断じてしていない! 我々は発言しようとして止められたのだ! 負けるかもしれないから戦わないというのは、千万歳までの不名誉だ!」と激しく反論し、議場は賛成派と反対派の怒号が飛び交う、大論争の舞台となった。
第三幕:司法大臣からの第二通告 ― 議会への挑戦状
議論が白熱する中、議長の中島が、一枚の書状を手に、神妙な面持ちで議場の静粛を求めた。
「静粛に! 静粛に願います! …ただいま、司法大臣より通知が参りました。…朗読いたします」
議場に緊張が走る。書記官長が読み上げるその内容は、まさに衝撃的としか言いようのないものだった。
【司法大臣からの通知書(12月4日付)】
【原文】「去月二十四日付ヲ以テ貴族院(※衆議院の誤記か)書記官長宛及御通牒置候處森時之助被告事件ハ本日落着依託金費消罪ニシテ刑法第三百九十五條ニ因リ重禁錮一箇年ノ刑ニ處セラレ候此段及御通知候也」【現代語訳】
「先月24日付で衆議院書記官長宛にご連絡しておきました、森時之助被告の事件ですが、本日判決が下りました。委託金横領の罪で、刑法第395条により、重禁錮1年の刑に処せられましたことを、ご通知申し上げます」
議場は、一瞬の沈黙の後、轟音のような喧騒に包まれた。
「何だと!」
「議会の許諾も得ずに、判決を下したというのか!」
井上角五郎が激高して叫ぶ。
「これは議会に対する冒涜だ! 司法大臣の処置は言語道断、議会を蔑視したものである! 断じて許すことはできない!」
議会が、自らの憲法上の権利について議論しているまさにその最中に、司法省は判決を下してしまったのだ。これは、政府・司法省による、議会への明確な挑戦状と受け取られた。
議論は、もはや森時之助個人の問題を離れ、議会と政府の権力闘争の様相を呈してきた。
「議長! 司法大臣をこの場に呼び出し、説明を求めるべきだ!」
「そもそも、24日付の最初の通知を、なぜ今まで議会に報告しなかったのか! 書記官長と議長の責任問題だ!」
植木枝盛らの厳しい追及が議長と書記官長に向けられる。
怒号とヤジが飛び交い、議場は収拾のつかない大混乱に陥った。結局、討論終局の動議が出され、採決の結果、末松三郎の動議、すなわち「会期前に逮捕され、会期後も拘留されている議員は、衆議院の許可なくして拘留を継続できない」という案が、圧倒的多数で可決された。
そして、この重大な問題に対処するため、末松三郎、井上角五郎、末松謙澄らを含む九名の特別委員が、議長指名によって選出された。議会は、政府・司法省に対し、敢然と立ち向かう姿勢を示したのである。
第四幕:議事堂から議員が消えた夜
しかし、この日の混乱はまだ終わらなかった。議事日程の第二番、「資格審査委員の選挙」が始まると、議論はまたしても手続き論の泥沼にはまり込んだ。
「資格審査委員は、常任委員会とすべきだ!」
「いや、議院法によれば、異議が生じたときに『特に委員を設ける』とあるから、特別委員会でなければならない!」
この問題を巡って延々と議論が続いた末、ようやく「特別委員会」を設けることで決着。続いて、委員の人数を「九名」とするか「十八名」とするかでまた紛糾。さらに、その選挙を議場で行うか、各部で行うかでもまた紛糾。
一つ一つの手続きに、これでもかというほど時間を費やし、議場は疲労の色を濃くしていく。ようやく、委員十八名を議場で投票によって選ぶことが決まり、投票が開始されたのは、すでに陽もとっぷりと暮れた後のことだった。
深夜まで長引く議論と投票に、議員たちの疲労はピークに達していた。開票作業が進む中、一人、また一人と、議員が音もなく議場から姿を消していった。
開票作業の途中、三十番の折田兼至が異変に気づき、叫んだ。
「議長に伺います! 段々と退席される議員が多いようですが、もし定足数を満たしていないのであれば、この会議は停会にしなければならないはずです! いかがか!」
<詳細解説:定足数>
議会が有効に成立するためには、総議員の3分の1以上の出席が必要とされていた。もし、出席議員がこの数を下回れば、その間の議事や議決はすべて無効となる。
議場はにわかに色めき立った。
「控え室にいる者もいるだろう」と副議長が取りなすが、駒林廣運が鋭く反論する。
「いや、控え室にはおりません! それは私が証拠立てます! なお、お調べを乞いたい!」
事態は深刻だった。もし定足数を割っていれば、この開票作業はおろか、この時間に行われている会議そのものが無効となる。
「定足数を満たしているか否か、調査を要求する!」
「調査が終わるまで、開票を中止せよ!」
しかし、副議長は「投票が済んだ以上、これを読み上げるのが先日の慣例でもありますから…」と、やや苦しい理由で開票を続行させる。これに反発した議員たちが、「こんな開票は無効だ! 私は帰る!」と叫びながら次々と退場していく。
議場に残った議員は、もはや数えるほどしかいない。その異様な光景の中、書記官が淡々と票を読み上げる声だけが、がらんとした空間に響き渡る。
すべての票が読み上げられ、九名の当選者が報告されたのは、深夜10時5分。ほとんどの議員が去った議場で、中島議長は疲労しきった声で、ようやく散会の辞を述べた。
憲法を巡る激しい論戦と、司法省からの衝撃的な通告、そして前代未聞の定足数割れ疑惑。第一回帝国議会は、その権威の根幹を揺るがす、あまりにも激しい嵐の夜を経験したのである。
第六章:議会の決断 ― 権力闘争の行方(明治23年12月5日)
第一幕:特別委員会の報告と、新たな火種
大混乱の夜が明けた12月5日、午後1時30分。議場には、昨日にも増して張り詰めた空気が漂っていた。前日選ばれた、末松三郎を委員長とする「議員逮捕事件に関する特別委員会」からの報告が、この日の議事の中心だった。
委員長の末松三郎は、報告を委員の一人である菊池侃二に委託。菊池が、委員会の結論を報告するために登壇した。
「委員会での決議をご報告いたします。報告書はすでにお手元に配布されている通りですが、決議は二つ。第一に…」
【委員会報告書案】
第一項「議員逮捕ノ事件ニ關スル本院本日ノ決議ヲ、議長ヨリ司法大臣ニ通知スルコト」
第二項「本事件ニ付キ司法大臣ノ照會アレバ、拘留ヲ許諾スベキモノト認定ス」【現代語訳】
第一項「議員逮捕の事件に関する、当衆議院の昨日の決議(=議会の許諾なく拘留はできないという決議)を、議長から司法大臣へ通知すること」
第二項「この事件について、もし司法大臣から照会があれば、拘留を許可すべきものであると認定する」
菊池は、この決議に至った経緯を説明した。
「第一項は、我々議会の明確な意思を政府に示すためのものです。我々は、司法大臣が我々の決議を重んじ、適切に施行されることを固く信じております。そして第二項ですが、委員会では意見が二つに割れました。一つは、司法大臣からの照会を待たずして、こちらから直ちに拘留を許諾する旨を通知すべきだという意見。もう一つは、あくまで司法大臣からの許諾要求を待ってから、許諾を与えるのが筋だという意見です。議論の末、委員会としては、まず我々の権利を主張した上で、もし司法大臣から正式な手続きによる照会があった場合には、我々は森議員の通常犯罪について拘留を許可する用意がある、ということをあらかじめ議会で決議しておくのが穏当である、と一致して結論いたしました。これは、我々が問題にしているのは、あくまで手続きの正当性であり、犯罪行為そのものを擁護するものではない、という議会の良識を示すためのものであります」
第二幕:「臆病者!」「敵を見ずに逃げるのか!」
この報告書に対し、議場から再び異論が噴出した。特に問題となったのは、やはり第二項だった。百八十二番の鈴木昌司が、厳しい口調で反論の口火を切った。
「私は、この委員会の報告に反対です! 特に第二項!『照会があれば許諾する』などと、なぜ我々が今から決めておく必要があるのか。我々が委員会に付託したのは、昨日の議決をどう実行するか、その手続きについてです。将来の仮定の話まで議決せよと、我々は委託した覚えはない! これは委員会の越権行為であり、断じて認めることはできない!」
この「越権行為」論に、多くの議員が同調した。さらに、九十四番の高梨哲四郎が、より痛烈な言葉で第二項を批判した。
「私も第二項には不同意であります! しかし、その理由は、越権だからというだけではない。私は、この報告案を出された委員諸公の、その心意気を問いたい! 昨日、あれほど勇ましく議会の権利を論じておられた方々が、一夜明けて、なぜこれほど弱腰な案をお出しになるのか! まるで、平家の公達が水鳥の羽音に驚いて逃げ出したという故事のようだ。敵の姿も見ぬうちから『もし攻めてきたら降参します』と決めておくとは、あまりに情けないではないか!」
高梨の痛烈な皮肉に、議場はどっと沸いた。「臆病者!」「そうだ、削除しろ!」というヤジが飛ぶ。
「これは、政府との無用な衝突を避けようという、政略的、権謀的な考えから出たものでしょう。しかし、私はそのような態度は好まない! 昨日の決議の精神に則り、ただ第一項の通知のみを行い、司法大臣の出方を待つべきだ。第二項は、ただちに削除されることを強く要求する!」
高梨の演説は、多くの議員の心を掴んだ。彼らは、政府に譲歩するような姿勢を見せることを、議会の恥と考えたのだ。
第三幕:最後の決着
委員の一人である末松謙澄は、「これは司法権との全面対決を避けるための、賢明な判断だ!」と必死に弁明したが、議場の空気は、もはや強硬論に完全に支配されていた。
委員会の報告書を巡る議論は、またしても紛糾したが、やがて討論終局の動議が出され、採決へと移った。
「では、決を採ります! 高梨君の動議、すなわち、委員会報告書の第二項を削除するというご意見に、ご同意の方はご起立!」
議場の圧倒的多数が、地響きのような音を立てて立ち上がった。
「多数! よって、第二項は削除いたします!」
中島議長の宣言により、衆議院の最終的な意思は、「まず、昨日の議決(=議会の許諾なく拘留はできない)を司法大臣に通知する」という、一点に絞られた。議会は、政府・司法省に対し、一切の妥協を排し、正面から対峙する道を選んだのである。
こうして、数日間にわたる大論争は、ひとまずの決着を見た。しかし、この後、司法省が議会の通知にどう応えるのか。議会の権利は、本当に守られるのか。その答えは、まだ誰も知らなかった。
この日、最後に議題となったのは、「政府委員の議席を、議員席より高い位置に設けるのは不当である」という動議だったが、これは否決された。小さな問題に見えるが、これもまた、議会と政府の間の、緊張感に満ちた力関係を象徴する出来事であった。
午後5時13分、散会。議員たちは、 ひどい疲労と、これから始まるであろう政府との本格的な対決への、静かな覚悟を胸に、議事堂を後にした。
【エピローグ:歴史の航跡】
第一回帝国議会は、その後も混乱と手探りの連続であった。
しかし、この初期の嵐のような日々は、決して無駄ではなかった。
議長選挙や全院委員長選挙で繰り返された紛糾は、議事進行における明確なルールの必要性を議員たちに痛感させた。この経験から「衆議院規則」が整備され、後の議会運営の礎が築かれていくことになる。その場でルールを作り、失敗から学び、またルールを修正していく。そのプロセスそのものが、日本の議会制民主主義の揺籃期の姿であった。
そして、森時之助議員を巡る「憲法第53条」の論争は、帝国議会がその歴史の初期において、自らの権利と権威をかけて政府と対峙した、最初の重要な事件として記録された。結果として、この時の議会の毅然とした態度は、政府に対して「議会は単なるお飾りの機関ではない」という強いメッセージとなり、後の議院内閣制へとつながる、議会の地位向上のための重要な一歩となったのである。
嵐の中から船出した日本の議会は、この後も幾多の荒波を乗り越えながら、歴史という大海原を航海していくことになる。その原点には、ガス灯の下で夜を徹して議論を戦わせた、羽織袴の男たちの情熱があった。
【まとめ:この日の議会】
この議会のポイントは3つ!
- ルールがない! まずはそこから! 議長選挙を始めようにも、投票方法、有効票の定義、同数票の扱いなど、何一つ決まっていなかった。全てのルールをその場で議論し、起立採決で決めるという前代未聞の状態でスタート。曾禰書記官長の「私の眼と根性で認めました」という発言は、この混乱の象徴だった。
- 憲法をめぐる大激突! 会期前に逮捕された議員の処遇を巡り、憲法53条「不逮捕特権」の解釈で議会が真っ二つに。「議会の権利を守れ」と主張する勢力と、「司法権の独立を尊重すべき」とする勢力が激しく衝突。議会が議論の最中に、司法省から「被告に判決を下した」との通知が届き、議会と政府の対立は決定的となった。
- 深夜の議事堂から議員が消えた!? 長引く会議に議員が次々退席し、議会成立の条件である「定足数(総議員の3分の1)」を割っているのでは、と大騒動に。議長が「投票中だから会議は続行する」と強行する中、議員が抗議して退場するなど、会議そのものが無効になりかける事態となった。